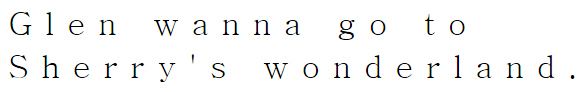
膝枕なんてしてやるのは初めてだった。何かねだられること自体が少ないのに、こんなに長時間くっついていられるスキンシップを望まれたのは意外でもあった。
「つか…… マジで膝で寝やがったよシェリー」
この状態だと体が動かせない。グレンは途方にくれて苦笑した。
不思議な夢の話をし、いつもよりちょっぴり甘えた仕草をするシェリーが新鮮で何だか可愛いと思った。気の強い彼女は、恥ずかしがってあまり甘えてこないのだ。
「なんか複雑だな」
自分と同じ外見だとはいえ、自分とは違う世界の住人であるメイ。シェリーがメイに好感を抱いていることは、グレンにとってちょっと不満だった。
それでも、誰もシェリーのことを知らない世界で、シェリーの帰りを保障したのは彼だ。その点では感謝している。
いや、全て夢じゃないか。
けれど、魔法も幽霊も存在するこの世界で、異世界が無いという話は逆に信じられない気がしてきた。
「またあいつのとこ、遊びに行ってるのか」
「んん……」
シェリーは少し体の角度を変え、何かを探るようにグレンの膝を撫でた。その手を握ってみれば、彼女は安心したように再び寝入る。
本格的に暇になり、グレンは庭へ目を向けた。
冷たく澄んだ空気と、葉を落とした街路樹が何ともこの季節らしかった。少し寒くなってきたけれど、シェリーから毛布を奪うわけにもいかない。
やることもないので庭のほうを見れば、シェリーが寝ていたカフェテーブルに、雑誌がおきっぱなしになっているのを見つけた。
取りに行こうかと思って腰を上げかけるが、シェリーが少し身じろぎしたのでそのまま動きを止める。まあ、気長に彼女が起きるのを待とう。
「このまま夜中まで起きなかったりして」
一人で呟いて笑うと、不意に外から声が聞こえた。
「遅刻ッ、おいどうすんだよ!」
「あ?」
聞こえた声はあまりに聞き覚えがありすぎるものだったので、自然と庭に目が言った。
その瞬間、白いスーツを着た金髪の男が、家の前の通りを忙しそうに駆け抜けていくのを見たような気がした。
所詮それは彼女の夢。
実際にシェリーが金髪男のメイについていってしまっていたのなら、グレンは今頃シェリーを探して延々と走り回っているはずだ。グレンは笑い、自分は少し疲れているのかと思う。
シェリーの赤毛を撫でると、彼女は少し身を竦めて腕を動かした。ずれた毛布をかけてやりながら、その髪をなで続けてやる。
早く帰って来ればいいと思い、直後に『何処から?』と自問する。
夢の世界か、はたまた異世界か。
その答えを知っているのは、彼女だけだろう。あるいは、彼女でさえその区別がついていないのかもしれない。
「あー、そっか。お前、約束守ってくれたのか」
そう思えばいい。
なんだか全てが良い方向におさまる答えが導き出せたようだ。グレンは満足して微笑する。
きっと今なら、自分も白兎のメイに会えるはずだ。
ベッドの柵に凭れ、グレンも目を閉じた。
グレン視点でしたとさ。
08/10/05/
もどる